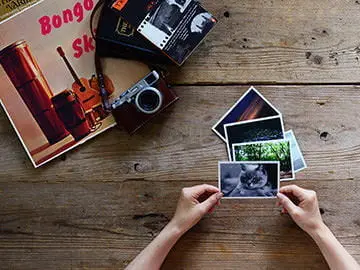こんにちは! 心斎橋本店のたつみです。
今年は残暑が長引き10月を向かえても夏日を超える日が続きましたが、急激に気温が下がり北日本では例年よりも積雪が観測されるなど、各地で「秋」を通り越して冬の様相となっている日本列島。。(-_-;)
まさに温暖化の影響でしょうか。。
日本古来の「四季」が何年後かには春秋が極端に短くなり「二季」になるとかもと言われてたり。。
そう考えると同じ景色に巡りあえる機会はどんどん少なくなるかも知れません今だからこそ撮れる写真がそこにあります!
カメラを持って出掛けましょう!
そして熱烈なファンが各地にいるとウワサで聞いた『Theマイナー機種列伝』!
第12回目のマイナーさんは 「ニコン F601M」の巻です
【AF一眼は第2世代へ】
カメラメーカー各社がピントの自動化を目指し、研究・開発を進めていた80年代。
プロ機F3の派生モデル「F3AF」で早く実用化にこぎ着けながらも、ミノルタの大逆転によりその後塵を拝する形となったニコン。
 1986年4月に発売したF-501はライバル追撃というよりは時間稼ぎ的な要素が強く、多くの支持を集めるまでにはいきませんでした。
1986年4月に発売したF-501はライバル追撃というよりは時間稼ぎ的な要素が強く、多くの支持を集めるまでにはいきませんでした。
このAF第一世代と呼ばれる期間はミノルタの圧勝となります。
しかし老舗メーカーとして確固たる地位と多くのファンを抱えているニコンが黙ってやり過ごしていた訳ではありません。
まずは測距センサーの内製化を目指します。
後に訴訟にまで発展するこの問題を早くから着目し課題解決に動きます。
「AM200」と名付けられた新型センサーを開発し、1987年6月に「F-401」を発売。第2世代へと歩を進めます。
さらに手を緩めず翌88年6月には早くもセンサーを改良(ニコンアドバンスAM200センサー)してハイアマチュア機種「F-801」の発売開始し多くの支持を取り戻します。
ニコンとして挑戦的であったこのF-801は、シャッターダイヤルを廃した他、ボタンによる操作を実現化し先進性を出します。
勢いづくニコンは同年12月にはAF最高機種として「F4」を完成させ市場に投入!
「ついにプロ機までもAFにするのか!」と世間の話題を独占(^^)v
もうこの頃には出遅れ感は全くなくAF一眼競争に突入する事となります
【実直な戦略】
第1世代の苦境を何とか乗り切り、自社センサーの開発と改良、さらに商品の充実で販売競争力を増したニコン。
89年4月にはアドバンスAM200を搭載することでF-401を改良 (F-401Sの発売)。
ブラッシュアップを行い商品力の向上を図るまさにニコンの生真面目さが伺えます。
さらに足場を固める為に新型機を準備します。
F-801(ハイエンド)とF-401S(初級者)の間を埋めるまさに第2世代の主力機として90年9月 「F-601」を発売します。
・当時ステータスとなっていたフラッシュを内蔵
・操作系は評判が良かったF-801を踏襲
・スポット測光搭載(801は非搭載)
・リチウムバッテリーを採用 などなど
この新型機は瞬く間に大ヒットします。まさに実直な戦略が実を結んだ時期でありました。
【販売戦略の裏側で】
ところがこのF-601発売と同時期に、ニコンは思わぬ一手に出ます。
F-601からオートフォーカス機能とフラッシュを省略したMF機「F-601M」を用意したのです。

本格的なAF一眼発売から既に5年余り。。
いまさらMF機!?との声はありながらも、未だ「写真はやっぱりMF!」という思想に配慮してという側面と、営業サイドからは海外需要として高機能で少しでも安いカメラが必要との思惑が重なった為と言われていますが真相は果たして。。(^^;
いずれにしても大人気となったF-601がベースですから品物自体悪くない(はず。。)
各社がMF機から遠ざかろうとする中、一石を投じそのファンをも取り込む事が出来るかも?と考えたかは知りませんが、果敢に勝負に出るニコンでありました。。
【次世代のMF一眼を志向するも。。】

先ずは基本スペックから。。
発売年月:1990年9月
・型式 モーター内蔵35ミリ一眼レフレックス電子制御式フォーカルプレーンシャッターカメラ
・マウント ニコンFマウント
・シャッター 1/2000~30秒及びBulb
・電源 6Vリチウム電池(DL223AまたはCR-P2タイプ)1個
・寸法 幅154.5mm 高96mm 奥行65mm
・質量 565g
・価格 65,000円
※上記は当時のメーカー製品カタログより参照
基本性能はF601と同一(兄弟モデルなんで当たり前ですが。。(^^;)
露出モードはマルチモード(プログラム&両優先AE)及びマニュアル。
プログラムAEについては当時主流になりつつあったマルチプログラムAEを採用。これによりプログラムシフトが可能となりました。
測光方式はお得意のマルチパターン測光と中央部重点開放測光(ただスポット測光が非搭載となった事は残念なポイント)
 操作系統はF801を踏襲。
操作系統はF801を踏襲。
上部左側に機能ボタン配置し、コストダウンの為にプラスチックからラバーへと素材変更されましたが、押し込みはむしろやり易くなり操作感は向上しました。
 機能切り替えの際にはいずれかのボタンを押しながら、右側パネル表示を見て電子ダイヤルを回して変更。
機能切り替えの際にはいずれかのボタンを押しながら、右側パネル表示を見て電子ダイヤルを回して変更。
シャッター最高速1/2000、連続巻き上げは秒2コマとF-801からスペックダウンしていますが通常撮影を主とした場合は十分な数値。
またMFカメラだけにファインダースクリーンはスプリットマイクロイメージに変更。初心者にも扱いやすい配慮を見せています。
中身はほぼほぼF601!(笑)
機能と操作感の向上を図った次世代のMF一眼レフ! 価格は65,000円とリーズナブルな設定(のはず)!
そうです!話題にならない訳がない??
と言いますか、いろいろ違う意味で話題にはなりました。。(-_-;)
オートフォーカス全盛期を迎えていた業界において何故いまさらMF?と当然の如く疑問を投げかけられます。
せっかくのMFも、基本AFレンズでなければ露出モードは制限されマルチパターン測光不可になる始末。。(つまり最大限の実力は発揮できない訳で。。)
さらに当時63,000円でNEW FM2を販売していましたし、AF機とはたったの15,000円差ではかえって割高感満載。。(ノД`)・゜・。アカンヤン
そもそもF601をMFで使えばええやんとか最大の特徴の内蔵ストロボ無ってどうなんとか正に本末転倒な状況。。( ゚Д゚)マジカ
こんな事が重なり合いしばらくの期間で販売終了。。
ニコンの目論見はあっという間に消え去ったのでした
【最後に。。】

新時代のMF一眼レフの在り方を模索したF-601M。。
しかし時代の大きな移り変わりの中で前世代的な考え方は受け入れられる事はありま
せんでした。
その後90年代半ばに掛けてますます各社の競争が激化!ニコンも全てのグレードでモデルチェンジを行い次世代へと移行します。
第2世代AF一眼の屋台骨を支えたF-601はお家芸でもあったセカンドモデルの登場なく、たった一代限りで終焉を迎えます。
あれから30年あまり。。
現在のフイルムブームの中で、大ヒットしたF-601は個体の多さと安価な一眼レフとして再び脚光を集めつつあるのに対し、F-601Mはほとんど市場で見ることはありません。
(了)