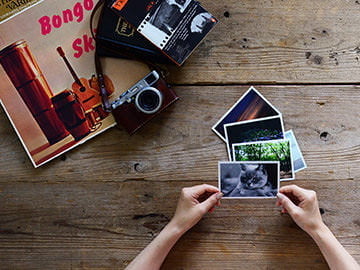こんにちは! 心斎橋本店のたつみです。
待ちに待った春を迎えたと思ったら、寒暖差のおかげもあり例年にも増して桜の見頃が長かったですね(^^♪
今年は上手く撮影出来ましたか?(笑)
などと言ってる間に最近では初夏と通り越し真夏のような熱気。。(-_-;)
気をつけないといけないのがそう「熱中症」。。
撮影に夢中になりすぎてしんどくならないようにこまめな水分補給を!( ゚Д゚)
ともかく絶好の季節です。カメラを持って出掛けましょう!
そして締め切りに追われながらも頑張って出筆している「Theマイナー機種列伝」!
第9回目のマイナーさんは 「オリンパス OM-2 SPOT/PROGRAM」(通称:OM-2SP)の巻です。
【質実剛健ないでたち】

現在においても小型・軽量で存在感を発揮しているオリンパス(現:OMデジタルソリューションズ)のカメラ達。
その原点となったのが1972年に登場した「OM-1」(発売時はM-1)。
プロカメラマンの使用にも耐えうることを目的とし、当時の一眼レフの代名詞でも
あった“三大悪”「デカく、重くて、やかましい」を克服するため、5年の歳月をかけて工夫に工夫を重ね究極とまで言わしめたコンパクトサイズと重量を実現。
シンプルで分かりやすい操作系も相まって、70年代以降のカメラの有り様を位置づけた代物として歴史に名を刻み大ヒット商品となります。
時は流れ、その3年後の75年11月に兄弟機「OM-2」が発売されるとOMシリーズは確固たる地位をつかみます。
機械シャッター&マニュアル露出機のOM-1に対し、OM-2は電子シャッター&絞り優先AE機でした。
とはいえ、開発はOM-1と同時期でパーツを共有化する事でコストを下げています。
このOM-2には、ライバル社に先駆けてた新機能・TTLダイレクト測光方式が搭載されていました。
それまでは、先に測光をしてから露光量を内部記憶しレリーズを完了させていたのを、ミラーアップ後、先幕が動き出すその瞬間に測光するという画期的な仕組み。
これにより露光中でも光量の変化に対応出来るなど様々なメリットが創出されます。
スゴイぞオリンパス!(てか開発陣!(^^;)
【発展改良を進む中で。。】
他社が機種ごとで手を変え品を変えたりする中でもオリンパスは実直な道を歩みます。
79年3月にOM兄弟の改良モデルを揃って発売。
部分改良(フラッシュの連動性向上など)ではあるものの、着実に製品熟成に掛けるオリンパスの「生真面目さ」がうかがい知れます(^^)v
さて、ここまで独自化を歩み世間の支持も得られ販売も好調であった訳ですが、技術革新の波は嫌でも押し寄せてきます。
キーワードはプログラムAEとより正確な測光の2点。
キヤノンを始めライバル社の多くはプログラムAE化に軸足を置きます。
まぁ~基礎的な部分は以前からあった訳でとっつき易かったという事です。
この時代の変化にどうするオリンパス(てか開発陣)
出した答えは測光方式の充実。
ここでも余所とは違う路線をあくまでも歩むことに拘りを見せます(想像です。。)
OMシリーズが10年を迎えた1983年10月にOM-2の後継モデルでマルチスポット測光を搭載したOM-4を投入。
↓先日、YouTubeで京都店の平田がOM-4Tiを紹介していましたね。
さらに翌年には兄弟機で1の後継機OM-3も発売しそれぞれを代替えさせます。
この2機種の登場は一躍話題となり一躍「オリンパス=スポット測光」のイメージが確立します。
どこまでもスゴイぞオリンパス(てか開発陣!)
残る課題はプログラムAE化。その頃、競合の各社は続々とプログラムAE機を発売開始していました。
78年4月 キヤノン A-1
↓
81年10月 ミノルタ X-700
↓
82年5月 ニコン FG
↓
83年3月 ペンタックス スーパーA
でも他社が先行する中でもオリンパスには焦りはありません(たぶんですが。。)虎視眈々とばかりに新型機の投入のチャンスを伺います。
機は熟したとばかりに1984年10月。
新しい武器となったスポット測光と待望のプログラムAEを搭載した新製品「OM-2 SPOT/PROGRAM」を満を持して投入する事となります。
【新旧プロセスの融合】

どのようなカメラだったのでしょうか?
先ずは基本スペックから。。
・発売年月:1984年11月
・型式 TTL自動露出式35㎜一眼レフカメラ
・マウント オリンパス OMマウント
・シャッター B・約1分-1/1000 ※自動露出制御時
・電源 :1.5V SR44またはLR44 2個
・寸法 幅136mm 高84mm 奥行50mm
・質量 540g
・価格 72,000円(ブラックのみ)
※上記は当時のメーカー製品カタログより参照
 露出モードは絞り優先AEとマニュアル露出。
露出モードは絞り優先AEとマニュアル露出。そしてオリンパス初となるプログラムAE機能を搭載した記念すべき機種です。
ボディ材質にも拘りを見せ骨格にはアルミダイキャストで堅牢度を確保!
また外装は当時自他社共に積極採用していたエンジニアプラスチックではなく高級機の証でもある真鍮を上部と底板に用いる念の入れよう(^^)v


軍艦部は先代OM-2/2Nからのデザインを引き継ぎ簡素で分かりやすいレイアウト。

巻き戻しノブ横に機能切り替えが素早くできるレバースイッチを配置。
 右側には露出補正/感度設定ダイヤルとレリーズ&巻き上げレバーのみのシンプル構造。
右側には露出補正/感度設定ダイヤルとレリーズ&巻き上げレバーのみのシンプル構造。
これだけで全ての制御をやってのけるとは凄いぞオリンパス!(てか開発陣(^^;)
内部機構として、AE時にはこれまたお得意のTTLダイレクト測光を。
そしてひとたびマニュアル露出にすればもう一つの売り物であるスポット測光へと瞬時に切り替わる設計。
先行のOM-4がマルチスポット対応だったのに対して1点スポットを採用。撮影時の微妙な露出調整はむしろスポットよりもやり易い事を意識してのこと。
どこまでも読みが深いぞオリンパス!(てか開発陣(^^;)
もちろん数多くの関連システムも使えて上位機種とは4万円程リーズナブル!
でもってこの本物感!
そうです!話題にならない訳がない!!(いつもありがとうございます(笑))
新旧機種の良いところを結集し、さらに念願のプログラムAEを手に入れてライバル社に立ち向かおうと意気揚々のオリンパス(てか営業部署)
ところがその僅か3ケ月後、あの「αショック」が勃発。。(-_-;)
世間の流れは一気にAF化の波に飲み込まれていきます。
本物感はどこ吹く風のようにほとんど注目されなくなっていき、オリンパスの野望は一瞬でしぼんでいくのでした。。
【最後に】
OMシステムの集大成として世に送られたOM-2 SPOT/PROGRAM。
正に質実剛健を具現化しながらまたしてもαの前に成す術もなく消え去った悲運の名機です。
もっと評価を受けても良かったはずが時代の荒波には勝てませんでした。
それほど多くの数が生産された訳ではなく、すでに40年以上経過しているために現在ではほとんど完動品を見かける事が少なくなりました。
もしどこかで見かけた時は是非とも手に取ってみて下さい。
当時の技術者の想いがそこに備わっているはずなので。。